いわゆるクラシック音楽とポピュラー音楽とのつながり
私はこのところ色々なジャンルのライブ、コンサートに出掛けます。
それぞれのジャンルで扱っている響きとその響きについてのトークが時々ジャンルを飛び越えてシンクロするときがあります。
あるコンサートライブ、篠笛(画像1 篠笛奏者 秋吉沙羅さん)とアイリッシュハープ(画像2 一般的なクラシック音楽で使用するハープより小型)、アイリッシュフルート(画像3 ケルト人の伝統音楽でよく使われている)、太鼓(画像4 和太鼓とのコラボが魅力)のジョイントライブがあり興味深い経験をしました。

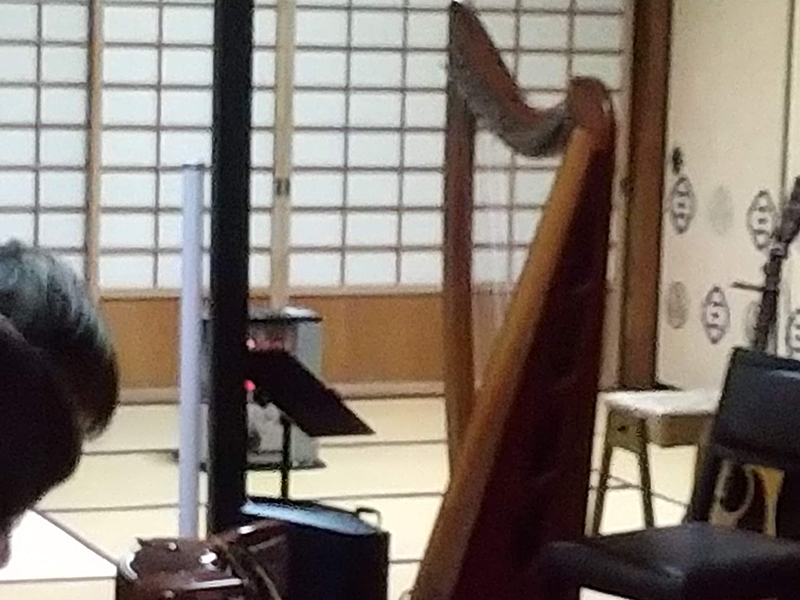


アイリッシュ音楽の中で「ジグ」というスタイルの音楽がありました。おそらく6/8拍子でにぎやかで、がちゃがちゃしたおもちゃ箱をひっくり返した素朴な音楽でした。そして連日他のコンサートでバッハのチェロ組曲の「ジーグ」を聞くチャンスに恵まれ、組曲の最後を飾る華やかなスタイルのものでした。
音の響きは全く異なるものの、この二つの音楽スタイル「ジグ」と「ジーグ」にはある種のリズム的な共通点と曲想の華やかさという点で、共通点を感じました。素朴な民族的な「ジグ」がある時代から上流階級のサロンあるいは宮廷に持ち込まれて「ジーグ」となり、バッハのチェロ組曲のように最終的に芸術音楽の一部を形作る楽曲として、歴史に刻まれたのではないか。こんなことを考えながらその時々の曲の響きを楽しみました。
このように音楽と触れた時に感じたことを少し歴史的に見つめなおしてみる、そんな楽しみ方をするときにちょっとした歴史書が役だったりするのです。音楽資料って音の響きをより深く味わうたすけになることがあるのです。一つの不思議な体験でした。
