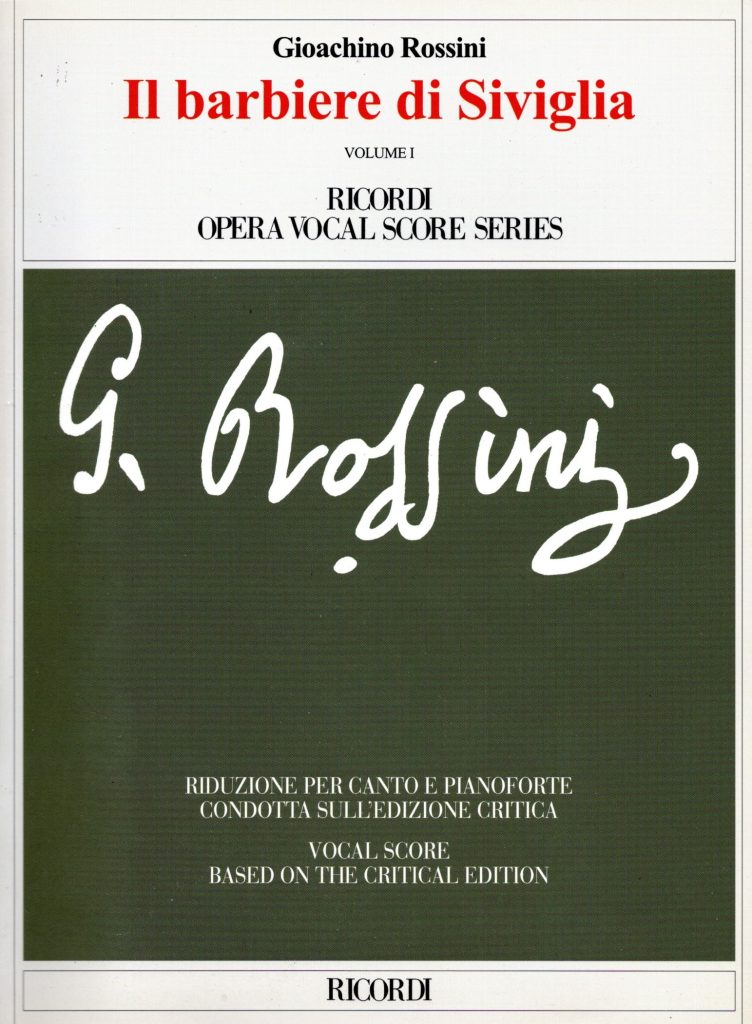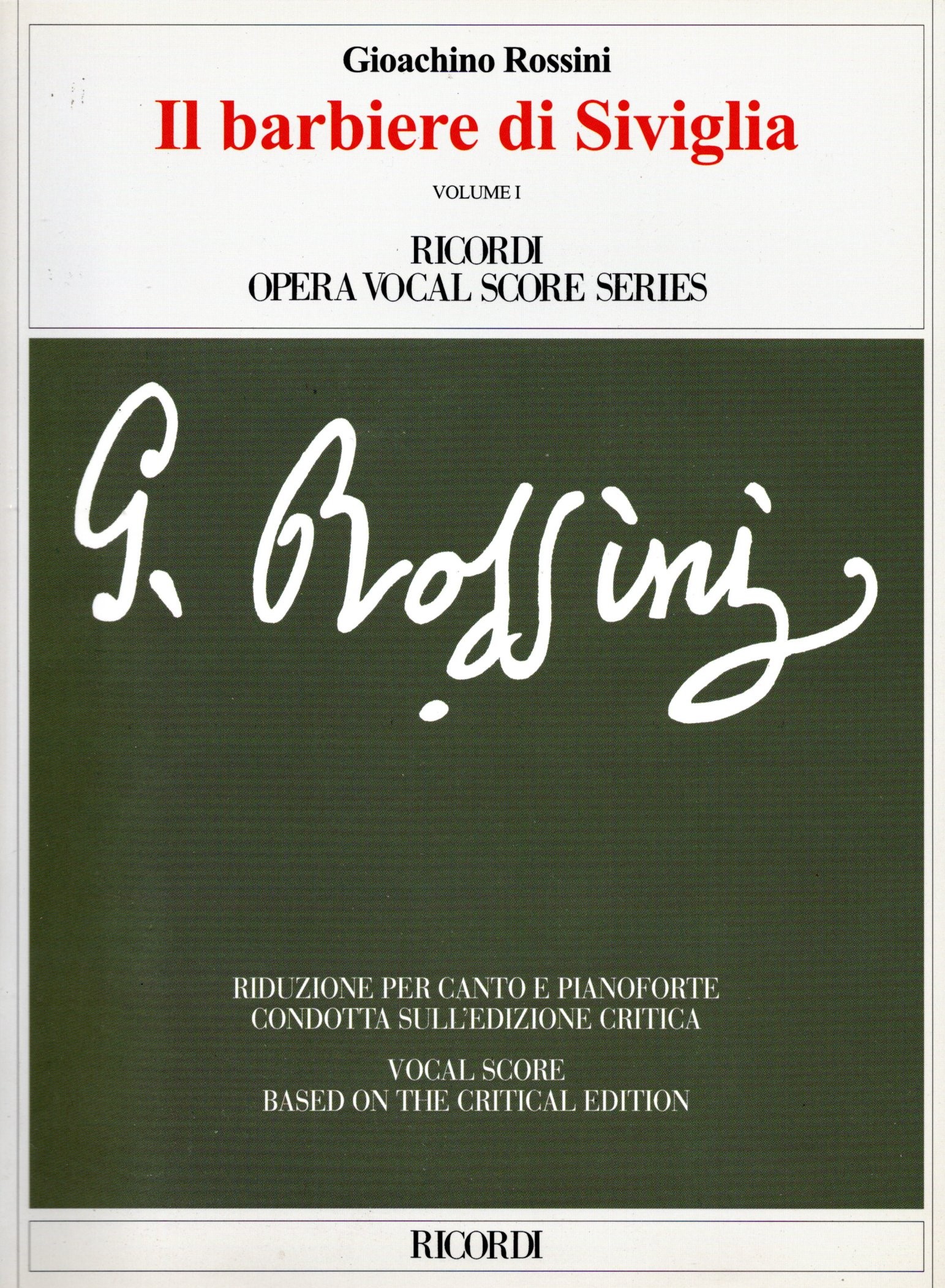劇場でオペラを観る、それは自ずと舞台での上演を観ることになる。舞台での上演という意味では、オペラであれ、演劇であれ同じ状況を指している。舞台上での物語があり、役を演じる衣装を身に着けた演者がいて、ドラマの状況を表す舞台装置や小道具、照明がある。これらが全て台本にそって進行される。オペラ上演と演劇上演において唯一異なるのが、楽譜の位置づけである。オペラにおいては、この楽譜という存在が、物語の時間の流れを規定する。
演劇にはこの時間の流れを規定する意味での楽譜という存在はない。楽譜は演劇でいう台詞回し、すなわち台詞の声の大きさや速さ、表情といった喋り方や間のとり方等が概ねあらかじめ規定されているのである。演劇でいう上演台本には上記の台詞回しに関して一般的には規定されず、稽古で演出家の指示で形作られていく。オペラにおいて台詞にあたる歌詞の扱い方は、音楽の範疇として指揮者が指示を出して、作り上げていくのが常である。
それでは、オペラにおいて演劇でいう上演台本の役割の一端を担うものは何かというと、それはリブレットと呼ばれるオペラ台本である。リブレットには通常、演劇の上演台本と同じく、役に沿って台詞があり、場面の説明であるト書きと呼ばれるものが記述されている。そこには筋書きが表されている。 先ほど、このリブレットのことをオペラにおいて演劇でいう上演台本の役割の一端を担うもの、と説明したが、あくまで、一端であって多くのことを語っているわけではない。前回、演劇での上演台本の意味合いは、原作が戯曲であると仮定して話を進めるとするならば、その原作戯曲を土台として上演に向けて新たに組み立てられた台本として機能していると述べた。この原作戯曲から上演台本を生み出す作業が原作戯曲を題材としてオペラ台本を作り上げる作業とある意味、言葉レベルで共通の作業をしているのではないかと思われる。原作戯曲からオペラが上演される形を生み出すために最初に取り組む作業として、オペラ台本の作成がある。このオペラとして成立する上演に向けて行うという点で、演劇においての上演台本作成と同様である。だが、オペラではこのオペラ台本を基に作曲家が音楽によって楽譜の形にまとめオペラを完成させるのである。この楽譜の形で作品となるため、オペラ台本のリブレットも完成したオペラ作品の一部分とみなされるのである。原作戯曲より上演台本を作成する演劇と原作戯曲よりオペラ台本を作成する作業のオペラと大きな目的としては上演を目的としているが、実質的な作業内容が全く異なっている。その異質な点が、オペラでは楽譜の作成のためのオペラ台本、リブレットであるということである。原作戯曲から上演に至るまでの過程においてオペラが演劇と決定的、かつ重要な違いを作り出しているというのが、楽譜の存在ということなのである。楽譜によってそのオペラの作品とみなされ、その作品としての意味合いは上演ごとに変化するものではない。おのずと楽譜に結び付いているオペラ台本も上演するごとに変化することは基本的にない。この点が上演ごとに変化する演劇の上演台本との最終的な違いとなる。
では、演劇における原作戯曲より上演台本を作り出す作業と、オペラにおける原作戯曲よりオペラ台本を生み出す作業の違い、あるいは一致しているところとがどのようであるのかを次の回より追及していきたい。